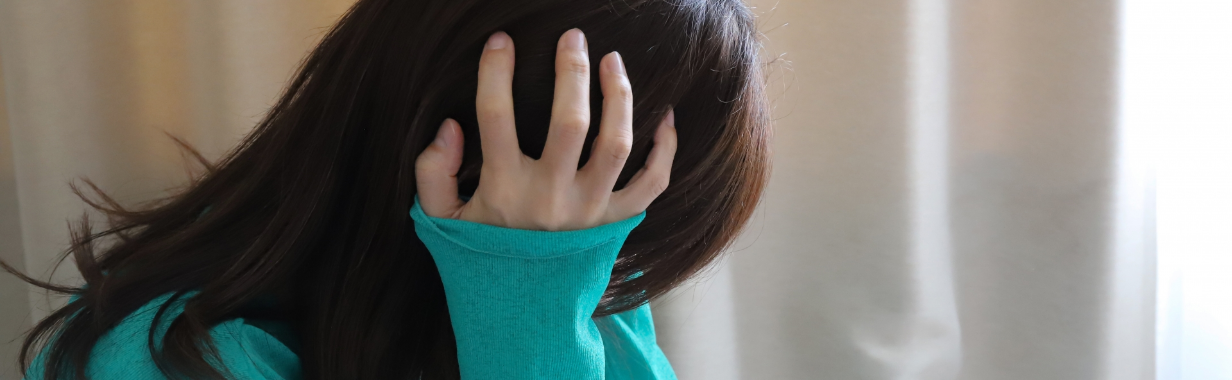近年、企業と従業員をカスハラから守るための社会的な動きが加速しています。その大きな一歩となったのが、改正労働施策総合推進法です。
2022年4月に施行されたこの法律の第33条第1項では、事業主に対して職場におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどと並び、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆる「カスタマーハラスメント」)に関して、事業主が講ずべき措置の検討を求めています。
これにより、カスハラ対策は企業の努力義務として明確に位置づけられました。
法律上、カスタマーハラスメントは「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者…の言動であつて…社会通念上許容される範囲を超えたもの」として定義されています。
これは、単なるクレームとは異なり、要求内容の過剰さや、暴言・威嚇といった手段の不当性、そして従業員の安全や業務を著しく損なう点が特徴です。
「カスハラ」と「クレーム」は何が違う?
多くの企業が直面するクレーム。しかし、そのすべてがカスハラに該当するわけではありません。
カスハラは、「社会通念上許容される範囲を超えた言動」と定義されます。
具体的な違いは以下のとおりです。
- カスハラの特徴
- 要求内容が不当または過剰
- 暴言や威嚇、長時間拘束など、手段・態度が威圧的
- 従業員の安全や尊厳、店舗業務を著しく阻害する
- クレームの特徴
- 商品やサービスに対する正当な改善要求
- 冷静かつ対話的な姿勢
- 業務の円滑な遂行を妨げない
カスハラの典型例
- 時間拘束
・時間を超える長時間拘束、居座り
・長時間の電話
・過度な要求 - リピート型
・頻繁に来店し、その度にクレームを行う
・度重なる電話
・複数部署にまたがる複数回のクレーム
・嫌がらせをつけたキャンセルの未払い、代金の返金要求
・備品を過度に要求する(歯ブラシ10本要望する等)
・入手困難な商品の過剰要求
・制度上対応できないことへの要求 - 暴言
・大声、暴言で執拗にオペレーターを責める
・店内で大きな声をあげて秩序を乱す
・大声での恫喝、罵声、暴言の繰り返し
・運行ルートへのクレーム、それに伴う遅延への苦情
・契約内容を超えた過剰な要求 - 対応者の揚げ足取り ・電話対応での揚げ足取り
・自らの要求を繰り返し、通らない場合は言葉尻を捉える
・同じ質問を繰り返し、対応のミスが出たところを責める
・一方的にこちらの落ち度に対してのクレーム
・当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な攻め立て - 脅迫
・脅迫的な言動、反社会的な言動
・物を壊す、殺すといった発言による脅し
・SNSやマスコミへの暴露をほのめかした脅し - セクハラ
・特定の従業員へのつきまとい
・従業員へのおいせつ行為や盗撮 - 優位な立場
・優位な立場にいることを利用した暴言、特別扱いの要求 - SNSへの投稿
・インターネット上の投稿(従業員の氏名公開)
・会社・社員の信用を毀損させる行為
クレーム対応の「法的義務」は存在しない
「お客様の要求には、どこまでも応じるべき」と考えていませんか?実は、企業や店舗側には、顧客との対話を続ける法的義務はありません。
たとえ要求の内容が正当であっても、その手段が不適切であれば、対応を打ち切ることは法的に正当な判断です。
例えば、長時間にわたる拘束や暴言がある場合、店舗内での対応を終了し、「今後は書面にてご連絡ください」と伝えることは、従業員の安全を守るために有効な手段です。また、自社の敷地内であれば、施設管理権に基づいて退去を求めることも可能です。
カスハラへの対応は、以下のように段階的に判断できます。
- 要求も手段も正当 → 誠実に応じる
- 要求は正当だが、手段が不当 → 要求内容には応じつつ、対応方法を制限・変更する
- 要求も手段も不当 → 一切応じず、記録を取って退去を求めたり、警察に通報する
カスハラ対策を怠った場合の罰則・リスク
カスハラから従業員を守ることは、企業の重要な責任です。しかし、企業として十分な責任を果たさなかった場合、どのような罰則が定められているのでしょうか。
現在のところ、カスハラ対策を怠った企業に対する直接的な罰則を定めた法律はありません。労働施策総合推進法が企業に求めるのは、対策を講じる「努力義務」です。この義務に違反しても、罰金や懲役といった刑罰は課せられません。
しかし、対策が不十分だと、以下のような間接的なペナルティとリスクが生じます。
- 行政指導と企業名の公表:対策が不十分であると厚生労働大臣が判断した場合、助言や指導が行われます。それでも改善が見られない場合は勧告が行われ、最終的には企業名が公表される可能性があります。これは企業の社会的信用を大きく損なう実質的なペナルティと言えます。
- 民事上の損害賠償:企業が適切な対策を講じなかったために従業員が精神的・肉体的な損害を受けた場合、被害を受けた従業員から損害賠償を請求される可能性があります。
これらのリスクは、単なる罰則以上の深刻な影響を企業に与えかねません。従業員の安全確保は、企業経営における重要なリスク管理の一つなのです。
悪質なカスハラへの具体的対応策
カスハラは、単なる迷惑行為にとどまりません。内容によっては、犯罪に該当する可能性もあります。
1. 悪質な口コミ投稿への対策
SNSやレビューサイトへの虚偽投稿、誹謗中傷は、名誉毀損罪や業務妨害罪に該当する可能性があります。
- 証拠の保全:投稿内容をスクリーンショットなどで記録しておきましょう。
- 削除要請:まずは投稿サイトの運営会社に削除を申請します。
- 発信者情報の開示請求:悪質な場合は、プロバイダ責任制限法に基づき、投稿者の特定を求めることができます。特定後、損害賠償請求も視野に入ります。
2. 暴言・暴行への対策
暴言は侮辱罪、土下座要求は強要罪、物を投げたり胸ぐらをつかむ行為は暴行罪に該当する可能性があります。
- 記録の徹底:ICレコーダーや防犯カメラで、音声や映像を記録することが重要です。
- 警察への通報:身の危険を感じた場合は、速やかに警察に通報しましょう。警察相談ダイヤル「#9110」も活用できます。
3. 無断撮影・録音への対策
従業員の顔を無断で撮影したり、その映像をSNSにアップする行為は、プライバシー権の侵害にあたります。
- 意思表示:毅然とした態度で撮影をやめるよう求めましょう。
- 掲示の設置:「撮影・録音禁止」の掲示を店舗内に設置するだけでも、抑止効果が期待できます。
- 退去要請と警察対応:要求に応じない場合は、退去を求め、それでも応じない場合は警察を呼びましょう。
最後に
カスハラから従業員を守ることは、企業の重要な責任です。問題が起きてから対処するのではなく、日頃から対応マニュアルを整備し、従業員に周知しておくことが重要です。
「誠実な対応を尽くした上で、それ以上の無理な要求には毅然と対応する」。この姿勢こそが、企業と従業員を守るための第一歩となるでしょう。
カスハラでお困りの際は、法的な観点から適切な対応をアドバイスできる弁護士にご相談ください。