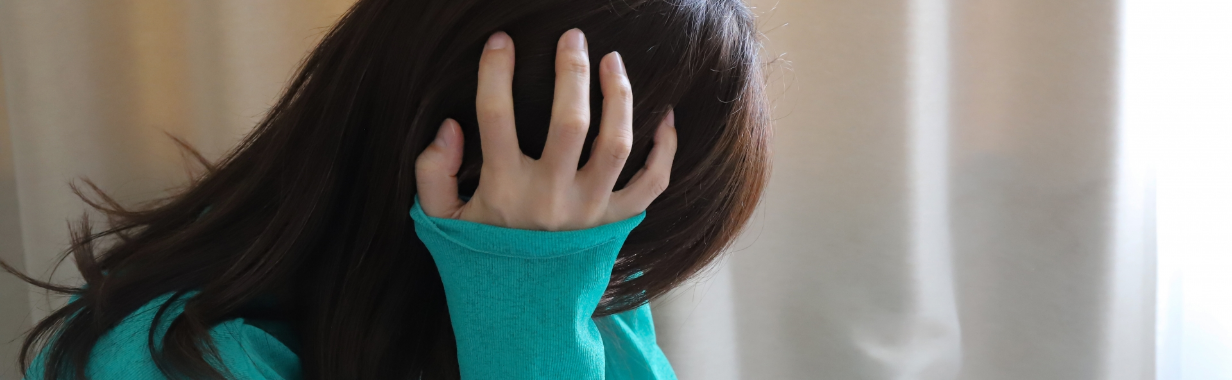※2025/11/28 東京地裁令和7年3月13日判決の解説を追加しました。
「部下から上司へのパワハラ」、通称「逆パワハラ」は、近年多くの企業で深刻な問題になっています。
しかし、法律上「逆パワハラ」という言葉は定義されていません。
重要になるのは、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が定める「優越的な関係」の解釈です。通常は「上司→部下」にある優越性が、特定の状況下では「部下→上司」へと逆転し、法的なパワハラになり得ます。
そのような優越性がない場合は、厳密にはパワハラとは呼べません。
今回は、「逆パワハラ」のような問題社員について会社の処分が争われた2つの事例(会社が敗訴したケース、勝訴したケース)を対比させながら、企業が踏むべき正しい手順を解説します。
逆パワハラは法律上の「パワーハラスメント」ではない
パワハラ防止法におけるパワハラは、以下の3つの要素をすべて満たす行為とされています。
優越的な関係を背景とした言動
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
労働者の就業環境が害されること
部下から上司への言動は、通常、職務上の地位や権限において上司が優越しているため、「優越的な関係を背景とした言動」という要件を満たしません。このため、原則として法的なパワハラには該当しないと考えられます。
しかし、厚生労働省の指針では、以下の要素がある場合、部下であっても上司に対して「優越的な関係」にある(=上司が抵抗・拒絶することが困難な状態にある)と認めています。
これらに該当する場合、部下の言動は単なる反抗を超え、法的なハラスメントとして認定されやすくなります。
① 知識・経験の差(ITスキルや専門技術)
部下が業務に関し豊富な知識・経験を持っており、その部下の協力がなければ業務が回らないケースです。
- 例: PCやシステムの知識がない上司に対し、IT担当の部下が「自分で調べてくださいよ」と協力を拒否し、業務を停滞させる。
② 人間関係・影響力(ベテラン部下と新任上司)
部下が職場内で強い影響力や人脈を持っており、上司が孤立しているケースです。
- 例: 勤続20年のベテラン部下が、異動してきたばかりの年下の上司の指示を公然と無視し、周囲もそれに同調するような状況。
③ 集団による行為(結託した攻撃)
複数の部下が結託して、一人の上司を攻撃するケースです。
例: 部下全員で示し合わせて上司の挨拶を無視したり、集団で吊るし上げのような抗議を行ったりする。権力」を利用して上司に不当な言動を取れば、優越的な関係を背景としたパワハラとみなされる可能性があります。
裁判例から学ぶ、懲戒処分の重要性と解雇の難しさ
法的には「パワハラ」でなくとも、「逆パワハラ」だ、「ハラスメント・ハラスメント」だと言いたくなる問題社員の存在に頭を悩まされる経営者は多いです。
問題社員への対応で最も難しいのは、「指導の方法」と「いつ、どの程度の処分を下すか」の判断です。
ここでは、対応のプロセスによって結論が分かれた2つの裁判例を紹介します。
事例①:「論破」を繰り返し、指導を拒否する新入社員(東京地裁 令和2年9月28日判決)
【どんな社員だったのか?】
入社直後から、上司の指導に対して独自の理屈で反論を繰り返し、長時間にわたる議論(いわゆる「論破」のような行為)で業務を停滞させました。「それは業務命令ですか?」「合理的理由を説明してください」などと繰り返し、改善が見られませんでした。
【会社の対応と判決 ⇒ 解雇は「無効」】
会社は「本採用拒否(解雇)」を行いました。しかし、原告の勤務態度に少なくない問題があったことは否定できないとしつつも、以下の理由から解雇を無効(不当解雇)と判断しました。
- 解雇事由の欠如
原告は実質的には新卒者と同じであり、会社が認識する問題に対して適切な指導を実施して改善されるか否かを検討した証拠がないこと。 - 退職勧奨目的の処遇
会社は原告の問題を改善させることと相容れない会議室に一人配置して自習させる処遇を主に続けさせており、この処遇や退職勧奨時の侮辱的な発言(「嘘ついてんだぞ、おまえ」など)は、不法行為にあたる。 - 結論
解雇は客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当ではない(解雇権の濫用で無効)。会社には未払賃金の支払いと、不法行為に基づく慰謝料などの損害賠償が命じられました。
事例②:上司をメールで罵倒し続けるベテラン社員(東京地裁 令和7年3月13日判決)
【どんな社員だったのか?】
銀行のベテラン行員(管理職)が、上司に対して侮辱的なメールを執拗に送りつけたり、同僚を公然と批判したりして職場環境を悪化させました。この社員は、上司や同僚に対し、以下のような攻撃的なメールを送信していました。
「上司の仕事に対する能力について尊敬できる点が殆どありません。もう少し社会人としての能力を上げてください」、「次回は、見逃すつもりも許すつもりもありません」
(同僚に対しCCメールで)「能力不足」「PCスキルが著しく低い」
【会社の対応と判決 ⇒ 降格・配置転換は「有効」】
会社は段階的に厳しい措置を取りましたが、裁判所はいずれも適法(有効)と判断しました。
- 懲戒処分
上司への侮辱や正当な業務指示への拒否を理由とした出勤停止処分。 - 大幅な降格・減給
管理職から非管理職への降格(月額約16万円の減給)…「管理職としての役割を果たしていない」という人事評価の正当性が認められました。 - 「一人部屋」への配置転換
周囲の社員が恐怖を感じてメンタル不調になるほどであったため、関連部署から離れた応接室(一人部屋)へ配置転換しました。裁判所はこれを「他の従業員の安全配慮のための措置」として、業務上の必要性を認めました。
会社が取るべき「問題社員」への対応策
これら2つの判決の決定的な違いは、「指導と改善プロセスの有無」です。
新入社員の事例では「指導不足」と判断され会社が負けましたが、ベテラン社員の事例では「再三の指導と面談」の記録があったため、厳しい処分が認められました。
① 「暴言」の証拠化
今回紹介した事例のように、具体的な発言内容やメール文面が、裁判での勝敗を分けます。「生意気だ」という主観ではなく、「いつ、どのような言葉で指示を拒否したか」を詳細に記録してください。
② 「指導」と「評価」のプロセス
令和7年の判決では、会社側が何度も面談を行い、人事評価(MBO)を通じて改善を促した実績があったからこそ、大幅な減給や降格が認められました。
「注意したが改善しなかった」というプロセスを積み重ねることが、厳しい処分の正当性を担保します。
③ 毅然とした「環境調整」
指導しても改善せず、周囲への悪影響(他の社員のメンタルヘルス悪化など)が大きい場合は、他の部署への異動や、物理的に座席を離すなどの措置を検討します。
「追い出し部屋(違法)」と言われないためには、「他の社員を守るため」という明確な目的と、業務上の必要性が必要です。
ハラスメントへの対応は弁護士にご相談ください
「部下が指示に従わず、現場が疲弊している」
「指導するとすぐに『パワハラだ』と言い返される」
このような問題社員への対応は、初期対応を誤ると問題が長期化・深刻化します。
経営者様・人事担当者様は、労働問題に強い当事務所にご相談ください。貴社の就業規則や実情に合わせ、法的リスクを抑えた解決策をご提案いたします。
従業員との労務トラブル・ハラスメント・不当解雇・残業代請求等労働トラブルに関するご相談は、労働問題に特化した弁護士にご相談ください
・完全予約制・プライバシー厳守
・文京区後楽園駅・春日駅すぐ/JR水道橋駅から乗り換え1本


当事務所では、不当解雇、残業代請求、パワハラ・セクハラ、退職勧奨など、働く人の権利を守るための労働問題全般を専門的にサポートしています。まずは詳細をご確認ください。
- 主な対応エリア
東京都文京区全域(小石川、春日、後楽園、本郷、白山、千石、茗荷谷、水道橋、音羽、関口、目白台など)
- 近隣の対応エリア
新宿区、千代田区、豊島区、台東区、中央区、港区、北区、荒川区、板橋区、練馬区など
- 利用可能な沿線
東京メトロ丸ノ内線・南北線、都営三田線・大江戸線、JR中央・総武線
- アクセス便利な駅
後楽園駅、春日駅、水道橋駅、飯田橋駅、本郷三丁目駅、茗荷谷駅、池袋駅、大手町駅、巣鴨駅
- ※全国からオンライン相談も承っております